当院について 当院の概要・沿革・施設基準
病院の概要

| 名称 | 富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒933-8555 富山県高岡市永楽町5番10号 |
| 電話番号 | TEL:0766-21-3930(代) FAX:0766-24-9509 |
| 病棟病床数 | 一般病棟 497床(開放型病床10床) うち救命救急病棟 8床 集中治療病棟 12床 NICU 3床 緩和ケア病棟 16床 地域包括ケア病棟 49床 |
| 外来病床数 | 外来人工透析 40床 薬物療法センター 17床 |
| 診療科目 | 【33科】 内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科・リウマチ科、糖尿病・内分泌・代謝内科、呼吸器内科、血液内科、腫瘍内科、脳神経内科、精神科、小児科、外科、消化器外科、乳腺外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科・IVR科、放射線治療科、麻酔科、救急科、緩和ケア外科、リハビリテーション科、歯科口腔外科、病理診断科、感染症内科 |
| 指定・承認事項 | 臨床研修指定病院 地域医療支援病院 救急指定病院 第2次救急輪番制病院 救命救急センター(第3次救急) 地域がん診療連携拠点病院 地域周産期母子医療センター 富山県DMAT指定病院 地域災害拠点病院 日本病院機能評価機構認定病院 教育施設指定 富山県地域リハビリテーション協力機関指定 難病医療協力病院 へき地医療拠点病院指定 DPC特定病院群病院指定 |
沿革
| 昭和11年10月1日 | 富山県購買販売利用組合連合会が農村振興と農民の福利厚生を目的として、現在地に産業組合高岡病院を開設(内科、小児科、外科、産婦人科、皮膚泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、理学診療科、歯科) |
|---|---|
| 昭和12年11月1日 | 富山県産業組合第一病院に名称変更 |
| 昭和18年11月25日 | 富山県農業会第一病院に名称変更 |
| 昭和18年4月1日 | 看護婦養成所開設 |
| 昭和23年8月15日 | 文厚連高岡病院に名称変更 |
| 昭和24年4月1日 | 協同組合高岡病院に名称変更 |
| 昭和26年4月1日 | 農協高岡病院に名称変更 |
| 昭和30年6月20日 | 診療棟及び病棟(円形棟)竣工 |
| 昭和30年7月1日 | 整形外科開設 |
| 昭和33年10月1日 | 総合病院承認 |
| 昭和34年1月22日 | 人間ドック開設 |
| 昭和35年1月1日 | 健康管理科開設 |
| 昭和38年4月1日 | 麻酔科開設 |
| 昭和39年5月9日 | 救急病院指定 |
| 昭和41年1月14日 | 放射線科開設 |
| 昭和41年8月23日 | 第2病棟竣工 |
| 昭和41年10月30日 | 皮膚泌尿器科を皮膚科と泌尿器科に分離 |
| 昭和43年10月1日 | 脳神経外科開設 |
| 昭和46年6月23日 | 第一病棟竣工 |
| 昭和49年6月6日 | 基準看護、一般442床、1類承認 |
| 昭和49年8月7日 | 診療管理棟(現西診療棟)竣工 |
| 昭和50年4月1日 | 厚生連高岡病院に名称変更 |
| 昭和50年7月1日 | 基準看護一般、473床特2類、結核80床特1類承認 |
| 昭和51年6月4日 | リハビリセンター竣工 |
| 昭和51年7月9日 | 形成外科開設 |
| 昭和52年3月31日 | 専修学校制度による看護専門学校設置認可厚生連高岡病院看護専門学校に名称変更 |
| 昭和52年8月11日 | 透析センター、検査センター竣工 |
| 昭和54年6月9日 | 基準看護一般、533床特2類、結核80床特1類承認 |
| 昭和54年6月30日 | 第2病棟増築工事竣工 |
| 昭和56年3月24日 | 看護専門学校竣工 |
| 昭和58年1月19日 | 第3病棟竣工 |
| 昭和59年1月24日 | 精神科開設 |
| 昭和59年9月1日 | 神経内科開設 |
| 昭和60年3月13日 | 臨床研修病院指定 |
| 昭和63年3月25日 | 中央診療棟竣工 |
| 昭和63年6月1日 | 基準看護一般、79床特3類、525床特2類、 結核50床特1類承認 |
| 平成2年4月1日 | 基準看護一般、82床特3類、580床特2類、 結核50床特1類承認 総合(農村)検診センター開設 |
| 平成2年6月1日 | 老人性痴呆疾患センター指定 |
| 平成3年8月1日 | 基準看護一般、257床特3類、405床特2類、 結核50床特1類承認 |
| 平成4年8月1日 | 基準看護一般、417床特3類、245床特2類、 結核50床特1類承認 |
| 平成6年4月20日 | 呼吸器外科開設 |
| 平成6年6月1日 | 結核病床50床廃止 |
| 平成7年2月16日 | 立体駐車場竣工 |
| 平成7年8月25日 | ハイム・フェルード(看護婦宿舎)竣工 |
| 平成8年4月1日 | 心臓血管外科開設 |
| 平成8年12月1日 | 歯科を歯科口腔外科に変更 |
| 平成9年4月1日 | 救命救急センター指定 地域周産期母子医療センター認定 一般病床672床 |
| 平成10年8月28日 | 一般病床の床増床(一般病床681床) |
| 平成11年5月28日 | 病棟増改築(東診療棟)竣工 |
| 平成11年7月1日 | 訪問看護ステーション開設 |
| 平成11年10月1日 | 居宅介護支援事業所開設 |
| 平成12年4月1日 | ライナック棟竣工、稼動 |
| 平成12年4月1日 | 消化器科開設 |
| 平成14年6月3日 | 院内LAN運用開始 |
| 平成14年7月1日 | 外来点滴センター開設 |
| 平成15年3月1日 | 回復期リハビリ病棟稼働 |
| 平成16年1月1日 | 電子カルテⅠ期稼働 |
| 平成16年9月21日 | 電子カルテⅡ期稼働 |
| 平成17年4月1日 | DMAT病院指定 |
| 平成17年11月21日 | 病院機能評価(ver4.0)認定 |
| 平成19年1月31日 | 地域がん診療連携拠点病院指定 |
| 平成19年4月1日 | 総合的がん診療センター開設 |
| 平成20年7月1日 | 一般病棟入院基本料7対1看護 |
| 平成21年1月31日 | 居宅介護支援事業所閉鎖 |
| 平成22年4月19日 | 富山県DMAT指定病院 |
| 平成22年11月21日 | 病院機能評価(ver6.0)認定 |
| 平成23年10月13日 | 一般病床 567床 |
| 平成24年3月12日 | 放射線診療棟稼働 |
| 平成25年3月25日 | 一般病床 565床 |
| 平成25年3月25日 | 西診療棟稼働 |
| 平成25年5月23日 | 地域医療支援病院 承認 |
| 平成25年10月1日 | 一般病床 562床 |
| 平成26年4月1日 | 放射線治療科、救急科 開設 循環器科を循環器内科に変更 |
| 平成26年5月1日 | 北診療棟稼働 |
| 平成27年3月26日 | 地域災害拠点病院指定 |
| 平成27年11月21日 | 病院機能評価認定更新(区分3rdver1.1) |
| 平成28年8月1日 | 緩和ケア病棟稼働 一般病床 533床 |
| 平成29年4月1日 | 地域包括ケア病棟稼働 49床 |
| 平成31年2月6日 | 富山県地域リハビリテーション協力機関指定 |
| 平成31年4月1日 | 難病医療協力病院指定、へき地医療拠点病院指定 |
| 令和元年9月2日 | 手術支援ロボット(ダヴィンチ)導入 |
| 令和元年10月1日 | がん温熱療法 高周波式ハイパーサーミア 治療システム導入 |
| 令和2年4月1日 | DPC特定病院群病院指定(初回) |
| 令和2年11月21日 | 病院機能評価(3rdG;Ver2.0) 第3回更新 |
| 令和4年2月1日 | 一般病床 517床 |
| 令和4年3月21日 | PET-CTを導入 |
| 令和4年4月1日 | DPC特定病院群 2回目認定 |
| 令和4年4月1日 | 地域がん診療連携拠点病院(高度型)指定 |
| 令和4年6月24日 | ISO 15189:2012認定(臨床検査部) |
| 令和6年4月1日 | DPC特定病院群 3回目認定 |
厚生労働大臣の定める掲示事項
1.当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
2.入院基本料について
当院は、急性期一般入院料(日勤、夜勤あわせて)入院患者7人に対して1人以上の看護職員を配置しております。なお、病棟、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なりますので、実際の看護配置につきましては、各病棟に詳細を掲示しておりますのでご参照ください。また、入院患者25人に対して1人以上の看護補助者を配置しております。
3.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について
当院では、入院の際に医師を初めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。
4.DPC対象病院について
当院は、入院医療費の算定に当たり、平成20年7月より、包括請求と出来高請求を組み合わせて算定する「DPC対象病院」となっております。
※医療機関別係数 1.5778(基礎係数 1.0718+機能評価計数Ⅰ 0.3952+機能評価計数Ⅱ 0.0888+救急補正係数0.0220)(令和7年6月)
5.明細書発行体制について
医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の判る明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、受診される診療科の窓口および総合受付2番窓口にてその旨お申し出ください。
6.当院は東海北陸厚生局長に下記の届出を行っております。
7.保険外負担に関する事項
当院では個室使用料、証明書・診断書などにつきまして、その利用日数に応じた実費のご負担をお願いしております。
1.特別療養環境の提供
特別療養環境室一覧
特別室・個室の提供について
・患者さんの病室として、特別室・個室をご用意しています。ご希望の場合は、病棟の看護師にご相談ください。
・ご利用される病室の料金は、以下の表の通りとなります。(消費税込価格です。)
室料差額料金表
特別室| 室料(税込) | 病棟 | 病室番号 | 設備内容 |
|---|---|---|---|
| 13,750円 | 1病棟7階 | 723 | 無料テレビ、トイレ、冷蔵庫(大型)、ソファー、ローテーブル、電動ベッド、クローゼット、チェスト、シャワー室、洗面台、ミニキッチン他 |
| 室料(税込) | 病棟 | 病室番号 | 設備内容 |
|---|---|---|---|
| 9,350円 | 緩和ケア病棟 | 501、502、503、505、506、507、508 | 無料テレビ、トイレ、洗面台、応接セット、ワードローブ、畳コーナー他 |
| 室料(税込) | 病棟 | 病室番号 | 設備内容 |
|---|---|---|---|
| 7,150円 | 中央病棟4階 | 151、152、160、161、162、165 | 無料テレビ、電動ベッド、洗面台、ソファー、ロッカー、エアコン他 |
| 室料(税込) | 病棟 | 病室番号 | 設備内容 |
|---|---|---|---|
| 6,600円 | 西病棟4階 | 401 | テレビ、トイレ、洗面台、チェスト他 |
| 室料(税込) | 病棟 | 病室番号 | 設備内容 |
|---|---|---|---|
| 6,050円 | 1病棟3階 | 315、316、317、318、320、321、322、323、325、326 | テレビ、トイレ、洗面台、チェスト他 |
| 1病棟4階 | 418、420、421、422、423、425、426 | ||
| 1病棟5階 | 517、518、520、521、522、523、525、526、527、528 | ||
| 1病棟6階 | 616、617、618、620、621、622、623 | ||
| 1病棟7階 | 717、718、720、721、722、725、726、727、728、730、731、732 | ||
| 2病棟4階 | 467、468、470、471、472、473 | ||
| 2病棟6階 | 667、668、670、671、672、673 | ||
| 西病棟4階 | 413、415、416、417、418 |
| 室料(税込) | 病棟 | 病室番号 | 設備内容 |
|---|---|---|---|
| 6,050円 | 中央病棟4階 | 168、170 | 無料テレビ、電動ベッド、ソファー、ロッカー、エアコン他 |
| 室料(税込) | 病棟 | 病室番号 | 設備内容 |
|---|---|---|---|
| 3,850円 | 1病棟6階 | 613、615 | テレビ、洗面台、チェスト他 |
| 室料(税込) | 病棟 | 病室番号 | 設備内容 |
|---|---|---|---|
| 2,750円 | 中央病棟4階 | 150 | 無料テレビ、電動ベッド、チェスト他 |
| 室料(税込) | 病棟 | 病室番号 | 設備内容 |
|---|---|---|---|
| 2,200円 | 1病棟4階 | 407、408、410、411、412 | テレビ、チェスト他 |
| 室料(税込) | 病棟 | 病室番号 | 設備内容 |
|---|---|---|---|
| 1,870円 | 中央病棟4階 | 158、166、167 | テレビ、チェスト他 |
| 室料(税込) | 病棟 | 病室番号 | 設備内容 |
|---|---|---|---|
| 1,870円 | 中央病棟4階 | 153、155、156、157 | テレビ、電動ベッド、チェスト、ソファー他 |
・ご利用日数に応じて、請求となります。(例:1泊2日の場合、2日分の請求となります。)
・妊婦の方は、消費税は非課税となります。(消費税法の規定による)
・なお、治療費とは別にご負担いただきます。
2.診断書・証明書及び保険外負担に係る費用
保険外負担に係る
一覧及び選定療養
対象外一覧
保険外給付(周産期関係)(令和6年11月現在)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 初診料 | 3,000円~ |
| 再診料 | 2,000円~ |
| 妊婦定期健診料 | 5,000円~ |
| 産褥健診料 | 5,000円~ |
| 新生児1ケ月健診料 | 5,350円~ |
| 免疫学的妊娠反応 | 2,500円 |
| 分娩料(院内分娩) 但し 双胎 5割加算 時間外 18時~22時 6時~8時 深夜 22時~6時 休日 帝王切開の場合は |
200,000円~ 220,000円~ 230,000円~ 230,000円~ 160,000円~ |
| 入院料(1日につき) | 保険点数に準じて自費算定 |
| 食事代(1食につき) | 保険点数に準じて自費算定 |
| 褥婦処置料(1日につき悪露交換・乳房マッサージ・育児指導含む) | 2,000円 |
| 新生児世話料(1日につき) | 10,000円 |
|
人工妊娠中絶手術(麻酔料・投薬・入院料を含む) 11Wまで |
90,000円~ 120,000円~ 150,000円~ |
| 永久不妊手術(帝王切開児は半額) | 120,000円~ |
| 避妊リング(麻酔料別加算) 挿入料 抜去料 |
35,000円~ 1,500円~ |
| 麻酔料 | 10,000円 |
| 経口避妊薬(21日分) 指導料を含む | 2,000円~ |
| 医学的指導相談料 | 3,000円 |
| 文書料 診断書・母性健康管理指導料 証明書 出生・死産証明書 出産手当金請求書 分娩費請求書 |
2,000円 1,500円 2,000円 1,000円 1,000円 |
| 風疹ワクチン接種料 麻疹・風疹混合ワクチン接種料 風疹免疫(抗体価)検査 B型肝炎ワクチン(バイオによる)接種料 ガスリー法採血料 ATL検査料(成人T細胞白血病) HIV検査料 |
6,300円(税込) 10,300円(税込) 3,560円~ 6,100円(税込) 3,500円 2,890円~ 2,500円~ |
| 子宮頸癌検診料 | 3,400円~ |
| 子宮頸・体癌検診料 | 8,600円~ |
| 感染症+の場合 | 10,000円 |
| 羊水染色体検査(外来検査及び1泊入院) 双胎の場合 |
125,000円~ 199,000円~ |
| 乳房マッサージ | 3,000円 |
| すくすく外来 | 2,500円(税込) |
| AABR(新生児聴覚検査) | 8,500円 |
| NST | 1,000円 |
| クアトロテスト | 12,000円 |
| ママの部屋(育児指導室)使用料(1日につき) | 5,000円 |
| 新生児マススクリーニング検査(手数料含む) | 9,110円 |
※自費診療においては、別途消費税を申し受けます。ただし、分娩料及び検診料等は非課税となります。
生活療養物品(周産期関係)
| 物品 | 金額 |
|---|---|
| 分娩セット(自然分娩・帝王切開) | 14,100円 |
| ※双子の場合 | 16,700円 |
| 新生児病衣 1日につき | 70円 |
| 新生児おむつ 1日につき | 340円 |
| 新生児清拭用ガーゼ 1箱 | 600円 |
| 新生児おしりふき 1個80枚入り | 140円 |
| NICU入院セット初回 1セット | 2,600円 |
| NICU入院セット継続 1セット | 1,400円 |
| K2シロップ 1回 | 30円 |
| HMS-1 1箱(100包) | 8,000円 |
| 体温計 1本 | 2,000円 |
保険外給付(文書料)
| 文書名称 | 金額(税込・1通につき) |
|---|---|
| 入院・通院・手術証明書 | 3,300円 |
| 通院証明書 | 1,100円 |
| 就労(就学)可否証明書 | 1,100円 |
| 一般診断書(勤務先・警察等) | 1,650円 |
| 公安委員会提出用診断書 | 1,650円 |
| 自動車税減免申請書 | 1,650円 |
| 身体障害者診断書・意見書 | 2,200円 |
| 難病医療費助成制度臨床調査個人票 | 2,200円 |
| 受診状況等証明書 | 1,100円 |
| 運動器損傷証明書 | 3,300円 |
| 死亡診断書 | 3,300円 |
| 死体検案書 | 4,400円 |
| 死亡診断書付入院証明書 | 6,600円 |
| 後遺障害診断書 | 5,500円 |
| 自賠責診断書・明細書 | 7,700円 |
| 国民年金・厚生年金診断書 | 5,500円 |
| 生命保険障害診断書 | 5,500円 |
| 妊娠・出産証明書 | 1,650円 |
| 出生証明書 | 2,200円 |
| 領収書再交付手数料 | 1,100円 |
※上記以外の文書料金については、文書受付にてお問い合わせください。
保険外給付(形成外科)(令和6年6月現在)
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 初診料 | 3,201円 |
| 再診料 | 836円 |
| マチワイヤー矯正 1趾 2趾 |
4,400円 8,800円 |
※上記診療の際には、別途診察料(初診料または再診料)をご負担いただきます。
保険外給付(予防接種料金)(令和6年10月現在)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 麻疹ワクチン | 6,300円 |
| 風疹ワクチン | 6,300円 |
| 麻疹・風疹混合ワクチン | 10,300円 |
| 二種混合ワクチン | 5,100円 |
| 四種混合ワクチン | 11,500円 |
| 五種混合ワクチン | 21,400円 |
| 流行性耳下腺炎ワクチン | 6,500円 |
| 日本脳炎ワクチン | 7,300円 |
| ロタウイルスワクチン | 9,300円 |
| Hibワクチン | 8,900円 |
| 水痘ワクチン | 8,400円 |
| B型肝炎ワクチン(ヘプタバックスⅡ0.5ml) | 6,300円 |
| B型肝炎ワクチン(ヘプタバックスⅡ0.25ml) | 6,100円 |
| 結核BCGワクチン | 10,900円 |
| 肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP) | 8,800円 |
| 肺炎球菌ワクチン(プレベナー20) | 12,300円 |
| 4価髄膜炎菌ワクチン | 25,400円 |
| 子宮頚がんワクチン(ガーダシル) | 17,800円 |
| 子宮頚がんワクチン(シルガード9) | 28,600円 |
| 帯状疱疹ワクチン | 23,500円 |
| RSウイルスワクチン | 32,400円 |
| インフルエンザワクチン(大人) | 5,400円 |
| インフルエンザワクチン(小人) | 5,100円 |
生活療養物品(令和7年4月現在)
| 物品 | 金額(税込) |
|---|---|
| 付添寝具 1日 | 200円 |
| 病衣 1日 | 70円 |
| おむつ 1枚 | 110円 |
| 新生児おむつ 1枚 | 374円 |
| 尿取りパット 1枚 | 30円 |
| スリッパ 1組 | 700円 |
| テレビおよび冷蔵庫利用代 1日 | 220円 |
| タオル(治療・看護に関係しない使用)1枚 | 110円 |
| 入れ歯保管容器 1個 | 80円 |
| DVD-R作成料 1枚 | 1,100円 |
| 心臓病教室のしおり 1冊 | 1,400円 |
| 診療情報開示用コピー代 1枚 | 20円 |
| その他のコピー代 1枚 | 10円 |
| 保険会社面談料 | 5,500円 |
| 保険会社文書照会 | 3,300円 |
| 救急車搬送料 | 当院規定料金 |
| 健康診断 | 保険診療相当額 |
| トコちゃんベルト M L LL |
6,050円 6,660円 7,380円 |
| USBメモリー | 1,210円 |
| マタニティブック | 950円 |
| エンゼルセット | 11,200円 |
| エンゼルセット(子供用) | 11,700円 |
3.初診・再診に係る費用の徴収
他の保険医療機関からの紹介によらず、当院に直接来院した場合については初診に係る費用として7,700円を徴収することになります。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、他の保険医療機関等からの紹介によらず来院した場合は、この限りではありません。(初診に係る選定費用をご負担いただく必要のない方は「選定療養対象外一覧」をご参照ください)。
また、再診患者さんの中で病状が安定し、診療所への紹介を受けた患者さんが、かかりつけ医の紹介無しに再受診された場合、あるいは「かかりつけ医」への紹介を当院より申し出たが引き続き当院にて診察を希望された場合(紹介状交付の有無に関わらず)につきましては、再診料のほかに保険外併用療養費として3,300円を徴収することになります。この費用は、病院と診療所の機能分担を推進する観点から、自己の選択に係るものとして、初診料を算定する初診に相当する療養部分についてその費用を徴収することが出来ると定めれられたもので、特定機能病院及び200床以上の地域医療支援病院に義務づけられております。
4.入院期間が180日を超える場合の費用の徴収
厚生労働大臣の定めるところにより、長期間入院されている方の入院料の一部保険給付から外され、特別の料金が徴収できる制度となりました。(入院期間は他の医療機関での入院期間を含む場合もあります)
これにより当病院では、下記の金額を請求させていただきます。なお、特別料金を請求させていただく方には、事前にご連絡いたします。
ご不明な点については、お気軽に医事課までお問い合わせください。
180日を超える入院に係る特別料金(税込)(令和7年2月現在)
| 入院料の区分 | 特別料金(1日につき) |
|---|---|
|
一般病棟入院基本料 急性期一般入院基本料 急性期一般入院料1 |
2,783円 |
8.特掲診療料の施設基準に係る院内掲示
別添の「施設基準に係る実績」をご参照ください。
9.ハイリスク分娩管理加算に係る院内掲示
別添の「施設基準に係る実績」をご参照ください。
11.オンライン資格確認を行う体制について
当院では、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。1階正面玄関ホールに設置されている「顔認証付きカードリーダー」に「マイナンバーカード」を置いていただくことで、簡単に認証(マイナ受付)ができます。
マイナ受付をご利用いただき、顔認証付きカードリーダーで「閲覧に同意する」を選択された場合、以下の情報を当院の医師が閲覧でき、より多くの情報に基づいた診療を受ける事が可能となります。
- 特定健診情報
- 診療/薬剤情報
※各種医療証(特定医療費(指定難病)受給者証、市区町村が発行する乳幼児医療証等)は、顔認証付きカードリーダーで承認することができません。
お手数をおかけしますが、マイナ受付実施後、初診の方は総合受付窓口、再診の方は受診される診療科窓口にてご提示ください。
※マイナンバーカードの健康保険証利用には、事前にご自身のスマートフォンで申込みいただくか、当院に設置している「顔認証付きカードリーダー」からもお手続きいただけます。
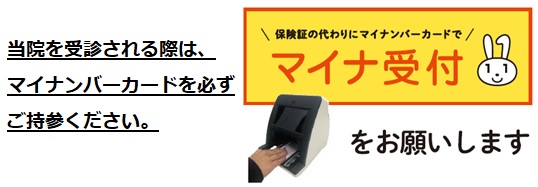
12.医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算に係る事項
当院では、医療DXを推進するための体制として、以下の項目に取り組んでいます。
- オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を活用して診療を実施しています。
- マイナ保険証を推進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
- 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの導入を検討しています。
14.がん性疼痛緩和指導管理料について
当院では、がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者さんに対し提供できる体制を有しております。
15.院内トリアージ実施料について
当院では、トリアージを行っています。
トリアージとは、診療前に看護師が症状を伺い、患者さんの緊急度・優先度を判断し重症の方に優先的な配慮をする方法です。
場合によっては診療の順番が前後することがありますがご理解をお願いいたします。
16.外来腫瘍化学療法診療料について
当院では、外来で抗がん剤治療を受ける患者さんが、安心・安全に治療を継続するために、以下の体制を整備しています。
- 医師、看護師を院内に常時配置し、患者さんからの電話等による緊急の相談に24時間対応できる連絡体制を整備しています。
- 緊急時に患者さんが入院できる体制を確保しています。
- 化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を定期開催しています。この委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師、業務に携わる看護師、薬剤師、管理栄養士、事務員で構成しています。
17.ハイリスク妊産婦共同管理料について
ハイリスク妊産婦共同管理料とは、ハイリスク妊婦又はハイリスク分娩に関する医学管理が必要となる患者さんについて、診療に基づき患者さんを当院に紹介した医師が、該当の患者さんが入院中である当院に赴き、当院の医師と共同で、医学管理等を行った場合に算定するものです。当院では以下の保険医療機関と連携し、ハイリスク分娩管理を共同で行っております。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 富山市立富山市民病院 | 富山県富山市今泉北部町2番地1 | 076(422)1112 |
| 高岡市民病院 | 富山県高岡市宝町4番1号 | 0766(23)0204 |
| 富山県済生会高岡病院 | 富山県高岡市二塚387-1 | 0766(21)0570 |
| 吉江レディスクリニック | 富山県高岡市野村1213-1 | 0766(26)1103 |
-
18.コンタクトレンズに係る診療について
19.歯科外来診療における医療安全対策
当院では、歯科外来診療に係る医療安全対策について、以下の通りに取り組んでいます。
- 医療安全管理体制の整備
医療安全管理者が中心となり、患者さんの安全を確保し、質の高い医療が提供できるよう医療安全管理体制を整備しています。 - 充実した緊急対応設備
安全な歯科医療環境を提供するために装置、器具等を設置しています。
<設置装置等>
・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
・血圧計
・救急蘇生セット - 安心の連携体制
他の医療機関や専門医との連携を強化し、迅速に対応できる体制を整えています。 - 情報公開と安全管理
診療内容や安全対策について患者さんや家族に分かりやすく説明し、ウェブサイトを通じて情報を公開しています。
- 医療安全管理体制の整備
20.その他
当院では、「患者相談窓口」を設置していますので、お気軽にご利用ください。診療内容に関すること、医療費に関すること、職員の接遇に関すること、退職後のこと、がんに関する色々な相談等、患者さんの立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをいたします。
当院では、安全な医療を提供するために、医療安全管理者等が医療安全管理委員会と連携し、より実効性のある医療安全対策の実施や職員研修を計画的に実施しています。
当院では、感染制御のチームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止等を行い、院内感染対策を目的とした職員の研修を行っています。また、院内だけにとどまらず、地域の高齢者施設や病院の感染防止対策の知識の向上のための活動を行っています。
当院は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責任と考えます。個人情報保護に関する方針を定め、職員及び関係者に周知徹底を図り、これまで以上に個人情報保護に努めます。
当院では、患者さんが安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、施設間の連携を推進し退院のご支援を実施しております。
当院では、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組みとして下記の事に取り組んでおります。
外来縮小の取組み、医師と医療関係職種における役割分担に対する取組み、医療関係職種と事務職員等における役割分担に対する取組み、医師の負担軽減に対する取組み、看護職員の負担軽減に関する取組み
当院では屋内外を問わず、「病院敷地内全面禁煙」となっておりますのでご理解とご協力をお願いします。
当院は厚生労働省指定の臨床研修病院です。指導医の指導・監督のもと、初期研修医が外来・病棟等で診療を行っております。また、看護師や薬剤師など様々な職種の実習生を受け入れている施設でもあります。日本の未来を担う医療職を養成するために、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
施設基準一覧(令和7年7月1日)
医療DX推進体制整備加算
地域歯科診療支援病院歯科初診料
歯科外来診療医療安全対策加算2
歯科外来診療感染対策加算4
歯科診療特別対応連携加算
一般病棟入院基本料
総合入院体制加算3
救急医療管理加算
超急性期脳卒中加算
診療録管理体制加算2
医師事務作業補助体制加算1
急性期看護補助体制加算
看護職員夜間配置加算
療養環境加算
重症者等療養環境特別加算
無菌治療室管理加算1
無菌治療室管理加算2
緩和ケア診療加算
栄養サポートチーム加算
医療安全対策加算1
感染対策向上加算1
患者サポート体制充実加算
報告書管理体制加算
褥瘡ハイリスク患者ケア加算
ハイリスク妊娠管理加算
ハイリスク分娩管理加算
呼吸ケアチーム加算
後発医薬品使用体制加算1
バイオ後続品使用体制加算
病棟薬剤業務実施加算1
データ提出加算
入退院支援加算
認知症ケア加算
排尿自立支援加算
地域医療体制確保加算
地域歯科診療支援病院入院加算
救命救急入院料4
ハイケアユニット入院医療管理料1
新生児特定集中治療室管理料2
小児入院医療管理料4
地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2
緩和ケア病棟入院料1
外来栄養食事指導料の注2に規定する基準
外来栄養食事指導料の注3に規定する基準
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算
糖尿病合併症管理料
がん性疼痛緩和指導管理料
がん患者指導管理料イ
がん患者指導管理料ロ
がん患者指導管理料ハ
がん患者指導管理料ニ
糖尿病透析予防指導管理料
乳腺炎重症化予防ケア・指導料
婦人科特定疾患治療管理料
一般不妊治療管理料
二次性骨折予防継続管理料1
二次性骨折予防継続管理料3
慢性腎臓病透析予防指導管理料
院内トリアージ実施料
外来腫瘍化学療法診療料1
連携充実加算
外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算
ニコチン依存症管理料
療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算
開放型病院共同指導料
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)
がん治療連携計画策定料
外来排尿自立指導料
ハイリスク妊産婦連携指導料1
ハイリスク妊産婦連携指導料2
肝炎インターフェロン治療計画料
薬剤管理指導料
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料
医療機器安全管理料1
医療機器安全管理料2
歯科治療時医療管理料
在宅患者歯科治療時医療管理料
救急患者連携搬送料
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2
在宅療養後方支援病院
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合)
遺伝学的検査の注1に規定する施設基準
染色体検査の注2に規定する基準
BRCA1/2遺伝子検査
先天性代謝異常症検査
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)
検体検査管理加算(Ⅳ)
国際標準検査管理加算
遺伝カウンセリング加算
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト
胎児心エコー法
神経学的検査
コンタクトレンズ検査料1
小児食物アレルギー負荷検査
内服・点滴誘発試験
経頸静脈的肝生検
CT透視下気管支鏡検査加算
有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査
画像診断管理加算3
ポジトロン断層撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る)
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く)
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る)
CT撮影及びMRI撮影
冠動脈CT撮影加算
外傷全身CT加算
心臓MRI撮影加算
乳房MRI撮影加算
小児鎮静下MRI撮影加算
抗悪性腫瘍剤処方管理加算
外来化学療法加算1
無菌製剤処理料
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
がん患者リハビリテーション料
歯科口腔リハビリテーション料2
多血小板血漿処置
人工腎臓
導入期加算2及び腎代替療法実績加算
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算
下肢末梢動脈疾患指導管理加算
ストーマ合併症加算
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
歯科技工加算1及び2
皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算
組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る)
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算
後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの)
椎間板内酵素注入療法
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))
緑内障手術(緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
緑内障手術(濾過胞再建術(needle法))
乳癌センチネルリンパ節生検加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用)
乳癌センチネルリンパ節生検加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独)
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)
気管支バルブ留置術
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
胸腔鏡下弁形成術
胸腔鏡下弁置換術
経皮的中隔心筋焼灼術
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー)
両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電極の場合)
両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合)
植込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び植込型除細動器交換術(心筋リードを用いるもの)
植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)、植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(心筋電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(心筋電極の場合)
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合)
大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方)
腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)
腹腔鏡下胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下噴門側胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの)
胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)
体外衝撃波胆石破砕術
腹腔鏡下肝切除術
腹腔鏡下膵腫瘍摘出術
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術
腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術
尿道狭窄グラフト再建術
人工尿道括約筋植込・置換術
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術に限る。)
周術期栄養管理実施加算
輸血管理料Ⅰ
輸血適正使用加算
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
胃瘻造設時嚥下機能評価加算
歯周組織再生誘導手術
麻酔管理料(Ⅰ)
麻酔管理料(Ⅱ)
放射線治療専任加算
外来放射線治療加算
高エネルギー放射線治療
一回線量増加加算
強度変調放射線治療(IMRT)
画像誘導放射線治療(IGRT)
体外照射呼吸性移動対策加算
定位放射線治療
定位放射線治療呼吸性移動対策加算
病理診断管理加算2
悪性腫瘍病理組織標本加算
看護職員処遇改善評価料60
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
入院ベースアップ評価料68
酸素の購入価格
施設基準に係る実績
医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む)に掲げる手術件数
当院における1月~12月までの各年について、手術の実施実績を皆様に情報開示します。
区分1に分類される手術
| 区分1に分類される手術 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
|---|---|---|---|---|
| ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 14件 | 19件 | 25件 |
| イ | 黄斑下手術等 | 80件 | 68件 | 75件 |
| ウ | 鼓室形成手術等 | 0件 | 0件 | 0件 |
| エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 128件 | 140件 | 123件 |
| オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 359件 | 419件 | 321件 |
区分2に分類される手術
| 区分2に分類される手術 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
|---|---|---|---|---|
| ア | 靭帯断裂形成手術等 | 12件 | 11件 | 10件 |
| イ | 水頭症手術等 | 18件 | 34件 | 36件 |
| ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 1件 | 1件 | 0件 |
| エ | 尿道形成手術等 | 16件 | 9件 | 10件 |
| オ | 角膜移植術 | 0件 | 0件 | 0件 |
| カ | 肝切除術等 | 43件 | 49件 | 52件 |
| キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 13件 | 14件 | 14件 |
区分3に分類される手術
| 区分3に分類される手術 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
|---|---|---|---|---|
| ア | 上顎骨形成術等 | 6件 | 8件 | 3件 |
| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 8件 | 9件 | 6件 |
| ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 1件 | 4件 | 2件 |
| エ | 母指化手術等 | 3件 | 0件 | 0件 |
| オ | 内反足手術等 | 0件 | 0件 | 0件 |
| カ | 食道切除再建術等 | 11件 | 9件 | 5件 |
| キ | 同種腎移植術等 | 0件 | 0件 | 0件 |
その他の区分に分類される手術
| その他の区分に分類される手術 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 人工関節置換術 | 108件 | 165件 | 153件 |
| 5 | 乳児外科施設基準対象手術 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 6 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 43件 | 49件 | 49件 |
| 7 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 49件 | 60件 | 66件 |
| 8 | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 234件 | 244件 | 198件 |
分娩件数
| 分娩件数(令和5年1月~12月) | 件数等 |
|---|---|
| 分娩件数 | 214件 |
| 産科医師 | 6名 |
| 助産師 | 13名 |
※医師等の人数は、令和6年1月1日現在のものです。
当院ではハイリスク分娩管理加算の施設基準の届出を行っています。
専従の産婦人科医師が3名以上、常勤の助産師3名以上を配置し、病院勤務医の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されており、産科医療補償制度に加入しております。
教育施設指定
| 担当科 | 設定団体 | 施設認定資格 |
|---|---|---|
| 内科 | (社)日本内科学会 | 日本内科学会認定医制度教育関連施設 |
| 日本高血圧学会 | 専門医認定施設 | |
| 糖尿病・ 内分泌代謝内科 |
(社)日本糖尿病学会 | 日本糖尿病学会認定教育施設 |
| 呼吸器内科 | 日本気管支学会 | 日本気管支学会認定医制度施設 |
| 循環器内科 | (社)日本循環器学会 | 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 |
| (社)日本心血管インターベンション治療学会 | 日本心血管インターベンション治療学会研修施設 | |
| 消化器内科 | 日本消化器病学会 | 日本消化器病学会認定指導施設 |
| 日本消化器内視鏡学会 | 日本消化器内視鏡学会認定指導施設 | |
| 日本肝臓学会 | 日本肝臓学会認定指導施設 | |
| 神経内科 | 日本神経学会 | 日本神経学会認定医制度教育関連施設 |
| 腫瘍内科 | 日本臨床腫瘍学会 | 日本臨床腫瘍学会認証施設 |
| 小児科 | (社)日本小児科学会 | 日本小児科学会認定医制度研修施設 |
| (社)日本周産期新生児医学会 | 周産期新生児専門医制度研修施設 | |
| 外科 | (社)日本外科学会 | 日本外科学会認定医制度修練施設 |
| 日本乳癌学会 | 日本乳癌学会認定医・専門医制度研修施設 | |
| 日本消化器学会 | 日本消化器外科学会専門医制度修練施設 | |
| 整形外科 | (社)日本整形外科学会 | 日本整形外科学会認定医制度研修制度 |
| 形成外科 | (社)日本形成外科学会 | 日本形成外科学会認定医研修制度 |
| 脳神経外科 | (社)日本脳神経外科学会 | 日本脳神経外科学会専門医認定制度指定訓練所 |
| 胸部外科 | 日本胸部外科学会 | 日本胸部外科学会認定医制度指定施設 |
| 日本呼吸器科学会 | 日本呼吸器科学会専門医制度認定施設 | |
| 日本脈管学会 | 腹部ステントグラフト実施施設 | |
| 皮膚科 | (社)日本皮膚科学会 | 日本皮膚科学会認定専門医研修施設 |
| 泌尿器科 | (社)日本泌尿器科学会 | 日本泌尿器科専門医教育施設 |
| 産婦人科 | (社)日本産科婦人科学会 | 日本産科婦人科学会専門医制度専門研修連携施設 日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設 |
| 眼科 | (社)日本眼科学会 | 日本眼科学会専門医制度研修施設 |
| 耳鼻咽喉科 | (社)日本耳鼻咽喉科学会 | 日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 |
| 日本気道食道科学会 | 日本気道食道科学会専門医研修施設(咽喉系) | |
| 放射線科 | (社)日本医学放射線学会 | 日本医学放射線学会専門医制度修練機関 |
| (社)IVR学会 | 日本IVR学会専門医修練施設 | |
| 麻酔科 | (社)日本麻酔学会 | 麻酔科認定病院 |
| 救急科 | 日本救急医学会 | 日本救急医学会認定医指定施設 |
| 画像診断 | 日本マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 | マンモグラフィ(乳房エックス線写真)検診施設 |
- なにかお探しですか?
- 休日・時間外について
- 交通アクセス
